
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/oslp/mokatsu.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/functions/diver_settings.php on line 513
Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /home/oslp/mokatsu.com/public_html/wp-content/themes/diver/lib/functions/diver_settings.php on line 522
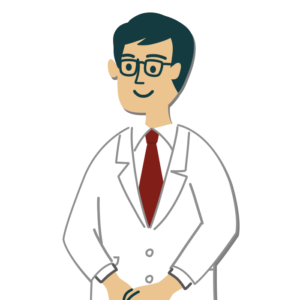
今回の記事のテーマは「法律からみた薄毛対策商品」です。
”法律”と聞くと難しいと感じたり、薄毛対策とはあまり関係ないと思われたりしてしまうかもしれません。
しかし、法律上の分類や広告規制の知識があれば、安心して薄毛対策の商品を購入することが出来るようになります。
難しいテーマではありますが、できるだけ分かりやすく説明していきたいと思います!
- 薄毛対策商品の法律的な知識が身につく
- 商品を選ぶ際に、商品説明を見て意味が理解できるようになる
- 発毛剤と育毛剤の違いがわかる
この記事の目次
医薬品と医薬部外品

育毛剤を始めとする薄毛対策商品の多くは、薬機法によって規制を受けています。
この法律の主な目的は「保健衛生上の危害の発生と拡大を防止」することです。わかりやすく言うと、「薬機法によって危険なものが販売されたり、誇大広告によって消費者が惑わされないようにすること」が目的です。
では、薄毛対策の商品が法律上どのように分類されているのか・なぜ規制しているのか、そして広告・記載上の規制はどうなっているのか見ていきましょう。
薬機法上の分類
薬機法第2条では、この法律の対象について定義を行っています。
ここで記されている事項を表でまとめると以下のようになります。
| 薬機法第2条の分類 | |
| 医薬品 | 人の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的 人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物 |
| 医薬部外品 | 人体に対する作用が緩和なもの 脱毛の防止、育毛のために使用される物(例示列挙部分) |
| 化粧品 | 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物 人体に対する作用が緩和なもの |
人体に対する影響の大きさは以下のようになります。
これは医薬品が人体に与える影響が強いため副作用も強くなり、医薬部外品は人体に対する影響が緩和なため副作用も弱くなることを表しています。
医薬品
医薬品は病気の予防や治療に使われる薬のことで、厚生労働省より配合されている有効成分の効果が認められたものです。
医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」と処方箋なしで購入できる「一般用医薬品(OTC医薬品)」があります。
「OTC医薬品」とは Over The Counter(オーバーザカウンター)の略語で、対面販売での購入が可能な医薬品のことを指します。
OTC医薬品はさらに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分けられます。
この中でも最も薬効と副作用が強いのは要指導医薬品です。
| OTC医薬品分類 | 概要 | |
| 要指導医薬品 | OTC医薬品として初めて市場に登場したもののため、慎重に販売する必要がある。
薬剤師が需要者の提供する情報を聞くとともに、対面で書面にて当該医薬品に関する説明を行うことが義務付けられている。 |
|
| 一般医薬品 | 第1類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。
販売は薬剤師に限られていて、販売店では書面による情報提供が義務付けられている。 |
| 第2類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。
専門家からの情報提供は努力義務。 |
|
| 第3類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で、第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。 | |
薄毛対策商品では、「発毛剤」が医薬品に該当し、「ミノキシジル」という発毛成分が含まれる場合、第1類医薬品に分類されます。
詳しい説明は2.育毛剤と発毛剤の違いで行います。
医薬部外品
医薬部外品は主に症状の予防・衛生を目的に使われるものであり、医薬品よりも緩やかな作用になります。
医薬部外品は医薬品よりも作用が緩和されているものの、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されています。
薄毛対策商品では「育毛剤」が主に該当します。
育毛剤は医薬部外品に分類され、影響力の大きさは医薬品と化粧品の中間的な立場にあります。
そのため、国に認可された育毛成分が配合され、かつ、副作用も抑えられるといったメリットがあります。後述する育毛関連の化粧品には、認可された成分が含まれていないため、効果の面で違いが生じます。
価格も医薬品の発毛剤と比べると、お手頃な商品が多いため多くの人にオススメすることができます。
詳しい説明は2.育毛剤と発毛剤の違いで行います。
化粧品
化粧品は身体を清潔にすることや外見の魅力を増すことが目的に使用される物を指します。
医薬部外品よりも緩やかな作用になり、薄毛対策商品では頭皮ローションやヘアトニックなどが該当します。
しかし、化粧品には厚生労働省で認可される育毛成分や殺菌成分などは含まれません。
どうして法律で規制するの?
では、そもそもなぜ規制が必要なのかを考えていきましょう。
薬機法は不良医薬品などを取り締まるために必要な規制を行ったり、医薬品や医療機器などの品質や有効性を確保することが目的です。
この目的を実現するために、医薬品などの生産や供給、及びそれらに関わる人たちに対しての許可などの規定が必要になります。
さらに、薬機法では医薬品などの広告についても規制を設けています。
例えば、化粧品のPRにおいて「確実に毛が生えてきます!」や「頭皮の殺菌効果があります!」と謳っている場合、化粧品であるのに医薬品や医薬部外品と誤解されるような表示がされているため規制対象となっています。
広告・商品で記載してはいけないこと
薬機法66条では誇大広告の規制を規定しています。
製造者や販売者だけでなく広告を掲載するメディアを含め、消費者に効能範囲について誤解を与えるような表現を行った場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が課されます。
効能範囲の解釈基準については、医薬品等適正広告基準で定められています。
ここでは、承認を受けた医薬品・医薬部外品・化粧品について、効能・効果の表現の範囲は承認を受けた効能効果の範囲を超えてはならないとしています。
例えば、医薬部外品である育毛剤の効能・効果については次のように規定されています。
| 育毛剤 | |
| 使用目的 | 脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤であること |
| 主な剤型 | 液状・エアゾール剤 |
| 効能または効果の範囲 | 育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛 |
この効能・効果の範囲を超え、消費者に効能範囲についての誤解を与えるような表現の場合には誇大広告に該当します。
特に注意が必要なのは、化粧品についての表現です。
化粧品では医薬部外品に認められている「肌荒れ・荒れ性」「にきびを防ぐ」「皮膚の殺菌」などの効能・効果は認可されなていないため、パッケージで表現することはできません。

育毛剤と発毛剤の違い

ここからは、代表的な薄毛対策商品である発毛剤と育毛剤の違いについて法律上の分類の違いからどのような差が生まれるのか、見ていきましょう。
発毛剤と育毛剤の効果
まず、二つの製品が法律上どのような分類になっているか一度確認しましょう。
発毛剤は医薬品、育毛剤は医薬部外品に分類されます。
つまり、発毛剤は「薄毛の治療」、育毛剤は「薄毛の防止・衛生」が主な目的となります。
この違いは人体に与える影響の強さの違いでもあるため、必然的に副作用の大きさも変わってきます。
| 製品 | 分類 | 目的 | 人体に与える影響 |
| 発毛剤 | 医薬品 | 薄毛の治療 | 大きい |
| 育毛剤 | 医薬部外品 | 薄毛の予防・衛生 | 発毛剤と比べると小さい |
配合されている成分
人体に与える影響力の差は、どの成分が配合されているかによって変わってきます。
それぞれの製品に含まれる代表的な成分について解説していきます。
発毛剤に配合される成分
公益社団法人日本皮膚科学会が発表した「日本皮膚科学会編 男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年版」において特に高く推奨された3種類の発毛成分をご紹介します。
- ミノキシジル
- フィナステリド
- デュタステリド
※5αリダクターゼとはAGA(男性型脱毛症)発症の原因となる酵素の一つ
上記の成分の中で、市販薬として唯一認められているのは、「ミノキシジル」です。
また、フィナステリドとデュタステリドは男性型脱毛症に対しては最も高い推奨度を与えていますが、女性型脱毛症に対しての使用はすべきではないとしています。
女性(特に妊娠中の女性)がフィナステリドやデュタステリドを服用すると、お腹の中の赤ちゃんに生殖器の発達異常などが生じるため、注意が必要です。
これに対して、ミノキシジルは男性型・女性型、問わず最高の推奨度を与えられいるため、幅広い人にとって有効な成分となっています。
育毛剤に配合される成分
育毛剤に含まれる成分の主な働きは以下の3つです。
- 成長促進
【毛母細胞活性化】
ステモキシジン,t-フランバノン,バントテニルエチルエテール等
【成長因子補足】
リジュリン、ツバメの巣エキス、リトオリゴベブチド-21(IGF)等
【血行促進】
イチョウ葉エキス、エビネエキス、L-アルゲニン等 - 脱毛予防
キャピキシル、冬虫夏草エキス、ノコギリヤシ、エチエルエストラジオール等 - 頭皮環境改善
【皮脂抑制】
アスコルピン酸、カシュウ、ビリドキシンBCI等
【保湿】
アロエエキス,イラクサエキス,アセチルグルコサミン,アルニカエキス等
【炎症防止】
イオウ、オウゴンエキス、ジフェンヒドラミンBCI,グリチルリチン酸ジカリウム等
【菌の増殖防止】
イソプロピルメチルフェノール,チョウジエキス,ヒノキチオール,ユーカリエキス等
成分の効果は上記3つに大きく分けられ、それぞれが働くことにより効果を発揮します。
詳しい説明はこちらの記事で書いています。
それぞれの副作用
効果・効能が強ければ副作用のリスクも上がってきます。
両商品の副作用の違いについて見ていきましょう。
市販で購入できる発毛剤にはミノキシジルが含まれているため、この成分の副作用についてチェックしていきます。
ミノキシジルには、以下のような副作用があります。

副作用の違いも参考の一つとして考えてみて下さい。
毛活Q&A


Q.育毛剤と発毛剤を併用しても良い?
A.併用してはいけません。
育毛剤・発毛剤に限らず、複数の種類の薬剤を同時に使用するのは望ましくありません。
その理由としては、以下のことが挙げられます。
- 成分の吸収を妨げる可能性がある
他の製品と併せて使用してしまうと、成分のバランスが崩れるため、有効成分が上手く吸収されず、本来の効果を発揮できない可能性があります。反対に、吸収量が基準値より増加してしまう場合があります。 - 副作用のリスクが高くなるため
相性の悪い成分が混ざりあい、頭皮トラブルが起こったり、重篤な副作用に繋がらうう可能性があります。
Q.副作用が出たらどうすればいい?
A.すぐに使用を中断し、症状にあった診療科を早めに受診しましょう。
- 頭皮のかゆみやフケ・かぶれなどの頭皮トラブルの場合
皮膚科での診断
- 動悸や発熱、男性器異常などの「体の不調」
内科での診断
まとめ
今回は法律上での薄毛対策商品の分類について解説した上で、発毛剤と育毛剤を比べて何が違うのかについて解説しました。
最後に、これから薄毛対策を始めたいと考えている方へ始め方のアドバイスをして終わりたいと思います。

②効果が薄ければ発毛剤を使用
③それでもダメならAGA治療








