
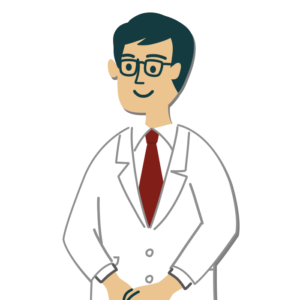
今回は「最先端の薄毛治療」についてご紹介していきます。
薄毛治療と聞くと、やはり“AGA”治療を想像する人が多いのではないでしょうか?
しかし、近年では科学技術の進歩により新たな治療方法が登場しています。
今回は、一般的なAGA治療と対比して、“ヒト幹細胞”を用いた薄毛治療や“iPS”細胞を用いた発毛実験についてご紹介していきます!
- 薄毛になってしまうメカニズムとは?
- 従来のAGA治療と新治療との違い
- ヒト幹細胞やiPS細胞を用いた最先端の治療について
この記事の目次
薄毛の原因
AGA治療及びヒト幹細胞治療はどちらも、「ヘアサイクル」の改善にフォーカスしています。
まずはヘアサイクルについて理解していきましょう。

ヘアサイクルとは、図のように毛髪が成長して古くなったら抜け落ち、また新しい毛髪が生えてくるという仕組みです。
ヘアサイクルには大きく分けて3つの段階があります。
| ヘアサイクルの段階 | 期間 | 詳細 |
| 成長期 | 約2年~7年 | 毛髪の元となる毛母細胞が細胞分裂をすることで、発毛して毛が成長していく時期 |
| 退行期 | 約3~4週間 | 毛髪が成長しきって、次第にそのスピードが落ちていき、最終的には成長が止まる時期。 |
| 休止期 | 数ヶ月 | 新たな毛髪が下から生え、古いものが抜け落ちる時期。 正常なヘアサイクルの場合、図の左側のように、生え変わりの循環が機能して強く太い毛髪が育っていきます。 |
しかし、AGA(男性型脱毛症)患者では右図のように毛髪の成長過程が阻害されてしまうため、十分に成長することなく、細く弱々しい毛髪となってしまいます。その結果、すぐに髪が抜け落ちやすくなり、髪が生えたとしても十分に成長しない状態となってしまいます。
従来のAGA治療

AGAは男性ホルモンの一種である「テストステロン」と「5αリダクターゼ」という酵素が結びつき、「DHT(ジヒドロテストステロン)」に変化してしまうことが一因の脱毛症です。
このDHTが毛髪を作る部分(毛母細胞)に作用し、毛の成長を妨げてしまいます。
AGA治療には2種類あります。
1つは5αリダクターゼの働きを阻害する「フィナステリド・デュタステリド製剤(5α-還元酵素阻害薬)」を使った治療。
もう一つは「ミノキシジル製剤」を使い発毛を促す治療です。
フィナステリド・デュタステリド製剤のAGA治療
フィナステリド・デュタステリド製剤は、どちらも5αリダクターゼを阻害する成分です。
「テストステロン」と「5αリダクターゼ」が結びついてしまうのを防いで、ヘアサイクルを改善していく治療法です。
つまり、AGAの進行を防止して、これ以上薄毛を悪化させないための治療法と言えます。
ミノキシジル製剤のAGA治療
ミノキシジル製剤は、毛根にある毛髪の元となる細胞「毛母細胞」に働き、活性化させます。
毛髪は毛母細胞が細胞分裂をすることによって生え、この分裂が多いほど強く太く育つことが出来ます。
つまり、ミノキシジル製剤におけるAGA治療は、毛母細胞の細胞分裂に重点を置き、とにかく髪を生やすことに注力する治療法と言えるでしょう。
ヒト幹細胞による再生医療

ここからは、ヒト幹細胞及びiPS細胞を用いた新しい治療法について解説していきます。
従来の薄毛治療法に対して、ヒト幹細胞による再生医療では「毛包ヒト幹細胞」にアプローチします。
この治療を理解するうえで、「再生医療とヒト幹細胞とは何か?」について説明していきます。
再生医療ってなに?
再生医療について、京都大学の研究所のサイトでは以下のように説明しています。
再生医療とは、病気や怪我などによって失われてしまった機能を回復させることを目的とした治療法です。
つまり、再生医療は壊れてしまって回復の見込みがない臓器や器官、組織を治療するときに使われます。
例えば、ある臓器が一定以上悪化して回復する見込みがなくなってしまった場合、その臓器を新たに作り出してしまうというのが再生医療です。
受精卵は1つの細胞が細胞分裂を繰り返し行うことで、人の体を作ります。そうであれば、受精卵のような細胞を作り、コントロールすることができれば壊れた臓器も再生できるのではないか、というのが再生医療の考え方です。
では一体、どんな細胞がこの夢のような医療を実現できるのでしょうか?
再生医療を可能とする幹細胞
再生医療を可能とするのは、ヒト幹細胞です。
幹細胞は、自己複製能と様々な細胞に分化する能力(多分化能)を持つ特殊な細胞である。この2つの能力により、発生や組織の再生などを担う細胞であると考えられている。
つまり、ヒト幹細胞とは「新しい脂肪」や「新しい血管」などに変身したり、他の細胞の活性化や自らを複製するなど様々な能力を持った細胞を言います。
後で登場するiPS細胞もヒト幹細胞の一種です。その他にも、胚性幹細胞(ES細胞)や成体幹細胞などが含まれます。
ヒト幹細胞を用いた薄毛治療

毛包の根元にはバルジ領域と呼ばれる部位があります。
このバルジ領域には毛を作る「毛包幹細胞」が存在し、休止期から成長期にかけて細胞分裂することで毛髪が形成されます。
しかし、毛包幹細胞の働きが悪くなってしまうと、休止期から成長期へのサイクルがストップしてしまい、ヘアサイクルの異常が発生してしまうのです。
ヒト幹細胞による再生医療では、異常が生じているヘアサイクルに対して、休止期から成長期への移行スイッチをONにし、毛包幹細胞の細胞分裂を活性化させることにより薄毛を改善させます。
ヒト幹細胞治療の効果
ヒト幹細胞を注入・塗布することにより、毛根の周辺に存在する「前駆細胞」が活性化します。この「前駆細胞」から作られる成長因子が休眠している毛包幹細胞に作用し、活性化することにより発毛スイッチがONになります。
従来のAGA治療が脱毛因子の阻害や細胞分裂の促進に注目していたのに対して、ヒト幹細胞による再生医療では異常をきたしている細胞を正常な細胞に置き換えるために、細胞に直接働きかける点です。
このように、従来とは全く違う視点からアプローチをすることにより、AGA治療を行います。
iPS細胞を用いた皮膚移植による再生治療

最後に、iPS細胞を用いた皮膚移植による再生医療についてご紹介します。
ヒト幹細胞による治療は、異常をきたしている毛包幹細胞を正常な細胞に置き換えるといった治療法でした。
次に紹介するiPS細胞を用いた再生医療は、あらかじめ毛の生えた皮膚を作ってしまい、それを移植するといった手法を取ります。
現時点では実験段階ですが、今後薄毛治療に活用できる可能性があります。
iPS細胞・再生医療とは?
まずはiPS細胞とは何かについてご説明します。
iPS細胞は、2006年に京都大学の山中伸弥教授によりマウス線維芽細胞にウイルスベクターを用いて4つの因子(Oct3/4, Flk1, Sox2, c-Myc)の遺伝子を導入することで、人工的にES細胞様の多能性幹細胞が樹立された。翌2007年には、同教授により、ヒトの細胞を用いたiPS細胞の作製にも成功し、成熟細胞のリプログラム(細胞の若返り)の可能性とともに、再生医療への応用など多くの分野で注目を浴びている幹細胞の一つである。
従来、ヒト幹細胞ではES細胞(胚性幹細胞)が代表的でした。ES細胞は胚盤胞(受精後6,7日目の受精卵)から作られ、人間のあらゆる組織や臓器の細胞を作り出すことが出来ます。しかし、子になる可能性を持った受精卵を壊してしまうことや患者さん由来のES細胞を作りづらいため拒否反応が生じやすいことなど、いくつかの問題点がありました。
iPS細胞が従来代表的であったヒト幹細胞と比較して画期的な点は、皮膚や血液などの採取しやすい体細胞を使って作ることができる点です。
これにより、患者さん自身の細胞からiPS細胞を作成できるため、移植した場合の拒否反応が起こりづらくなります。
このような特徴を活かして、細胞を移植する細胞移植治療への応用が期待されています。
培養皮膚をマウスに移植
では、実際に薄毛治療においてiPS細胞を用いて細胞移植を行った実験についてご紹介します。
この実験では
「iPS細胞から毛の生えた皮膚細胞を作りだし、それをマウスに移植すると毛は生えるのか」
ということについて検証しています。
実験の概要
| 培養皮膚をマウスへ移植 | |
| 1 |
|
| 2 |
|
この研究はアメリカ、ボストン小児病院のイ・ジュン氏らによってまとめられ、2020年6月3日に最も権威ある学術雑誌「nature」に掲載されました。
実験結果からわかること
この実験結果から、人間に対して培養皮膚の移植が行われた場合にも細胞の再配列が行われれば、正常な毛が体の外部に向かって生えることが期待できます。
そして、毛の生えた皮膚を無制限に作り出すことが出来れば、薄毛を根本的に治療する方法になるかもしれません。
まとめ
今回は最先端の薄毛治療についてご紹介しました。
将来的にはヒト幹細胞を用いた発毛がスタンダードとなるかもしれません。
技術がどんどん進化している世の中で、将来どんな治療法が出るか楽しみですね。
最新の情報を取り入れつつ、自分に合わせた最適な治療法を選択してください!







